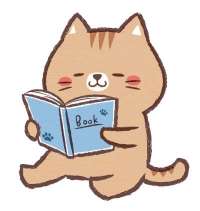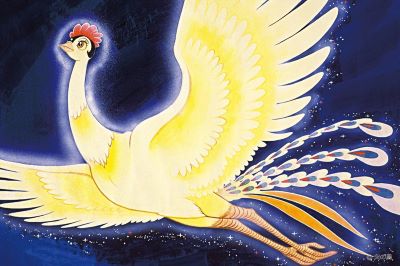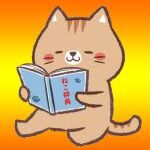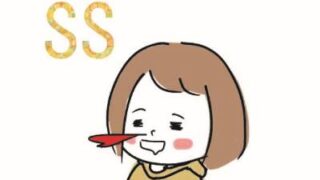いわずと知れた日本世界に誇る「千と千尋の神隠し」
2024年に「君たちはどう生きるか」が長編アニメ映画賞を受賞するまで、日本の長編アニメーション作品で唯一アカデミー賞を獲得した作品でした
金曜ロードショーで何度も放送されていますが、何度見ても飽きないと毎回見ている人も多いのではないでしょうか?
今回はそんな千と千尋をさらに面白く掘り下げてくれる台詞を取り上げました。
- 母 「石の祠(ほこら)。神様のおうちよ」
- 千尋 「おかあさん、あの建物うなってるよ。」
母 「風鳴りでしょ。気持ちいいとこねー、車の中のサンドイッチ持ってくれば良かった。」 - 湯婆婆 「ここはね、人間の来るところじゃないんだ。八百万(やおよろず)の神様達が疲れをいやしに来るお湯屋なんだよ。 それなのにおまえの親はなんだい?お客さまの食べ物を豚のように食い散らして。当然の報いさ。 おまえも元の世界には戻れないよ。」
- 兄役 「ええい、静まれ!静まらんか!!下がれ下がれ!」「 これは、とんだご無礼を致しました。なにぶん新米の人間の小娘でございまして…」
- 釜爺 「えーんがちょ、せい!えーんがちょ!!」
- 湯婆婆 「これっぱかしの金でどう埋め合わせするのさ。千のバカがせっかくのもうけをフイにしちまって!」
- 銭婆 「あたしたち二人で一人前なのに気が合わなくてねぇ。ほら、あの人ハイカラじゃないじゃない? 魔女の双子なんてやっかいの元ね。 おまえを助けてあげたいけど、あたしにはどうすることも出来ないよ。この世界の決まりだからね。 両親のことも、ボーイフレンドの竜のことも、自分でやるしかない。」
母 「石の祠(ほこら)。神様のおうちよ」

【祠(ほこら)】
鳥居のない小さな社殿(しゃでん)の事
社殿とは神社にある主要な建物の総称 神様が鎮座する「本殿」や参拝者が礼拝する「拝殿」などが含まれます 全ての神社に全ての建物があるわけではなく規模によって様々です
祠にはその家と土地を守ってくれる神様が祭られていて、祭られている神様は一つの祠に1体というわけではなく1体の事もあれば何体も祭られていることもあるようです
千尋がみた石の祠は一つではなく沢山描写されていました
一つの祠に複数の神様がいる可能性もある事を考えると、とても沢山の神様が祭られているという事を描写しており、物語の伏線になっています
崖の上には稲荷神社の祠があった。このごろのこととて屋根はやぶれ軒は傾き、誰も番をしていない祠だった。春木は、その石段をのぼることをわざとさけ、横の方についている草にうずもれた急な小道をのぼっていった。
海野十三「少年探偵長」
千尋 「おかあさん、あの建物うなってるよ。」
母 「風鳴りでしょ。気持ちいいとこねー、車の中のサンドイッチ持ってくれば良かった。」

【風鳴り】
風が鳴る音。特に決まった音ではなく様々な文脈で使われる。
同時に武士の長身は、敵の中へ飛び込んでいた。ピューッという風鳴りの音、続いて賊どもの倒れる音、そうして軟らかい気合いと共に、武士の姿は帆柱のもとに、端然冷然と立っていた。
国枝史郎「名人地獄」
犀川の上流で、やや遅れぎみの若葉が淵の上を半分以上覆いかぶさって、しんと、若葉の風鳴りがすると、それにつれて、淵の蒼い水面に鱗がたのさざなみが立って、きゅうに涼しさと寒さとが一どきに体温にかんじられた。
室生犀星「蛾」
ひと雨降つて晴れたと思ふまに、凄まじい大きな、ちやうど獣の咆えるやうな、風鳴りがしました。
小熊秀雄「小熊秀雄全集-14」
竹垣や柵、電線や物干し竿などに強い北風が当たり、ヒューヒューと笛のように鳴る音の事を虎落笛(もがりぶえ)といい冬の季語になっています
千尋が聞いた風鳴りはどんな音だったのでしょうか そんなことを考えながらもう一度見るのもいいかもしれません
虎落笛の詳細はこちらから

湯婆婆 「ここはね、人間の来るところじゃないんだ。八百万(やおよろず)の神様達が疲れをいやしに来るお湯屋なんだよ。 それなのにおまえの親はなんだい?お客さまの食べ物を豚のように食い散らして。当然の報いさ。 おまえも元の世界には戻れないよ。」
【八百万(やおよろず)】
数が非常に多い事。数えきれないほど多い事。

神道では「八百万の神」といい自然界の全てのものに神様が宿るという思想が生まれました
このような背景から「八百万」は豊かな自然観、信仰を反映した象徴的な語源をもつ言葉として単なる数字ではない意味を持っています
のみならず世上は八百万の神々が出雲の大社へ旅立をせられて、いずれの社もその御留守の即ち神無月であると思うと一層の寂しさを覚える
高浜虚子「俳句はかく解しかく味う」
兄役 「ええい、静まれ!静まらんか!!下がれ下がれ!」「 これは、とんだご無礼を致しました。なにぶん新米の人間の小娘でございまして…」
【新米(しんまい)】
仕事などを新しく始めたばかりでまだ慣れない人の事
なぜ仕事に慣れない人の事を新米と呼ぶのかはいろんな説がありますがその中の一つをご紹介
【新前掛け説】江戸時代に新しく奉公した人が新しい前掛けをしている事から「新前掛け」と呼ばれていた それが略されて「新前」」更に転じて「新米」となったという説

だから私が知った時はまだそのカフエエへ奉公に来たばかりの、ほんの新米だったので、一人前の女給ではなく、それの見習い、―――まあ云って見れば、ウエイトレスの卵に過ぎなかったのです。
谷崎潤一郎「痴人の愛」
釜爺 「えーんがちょ、せい!えーんがちょ!!」
【えんがちょ】
不浄なものに触れた人を子供がはやし立てる言葉、不浄なもの、穢れの感染を防ぐための仕草の事。主に関東の方言とされており、時代や地域によって、「バリアー」「エンガ」「ビビンチョ」「エンピ」など様々な言い方がある

二〇四号室の七人にとって、手塚との生活は、しだいに不快なものになっていった。
だが、慶一には娯楽室の生活があったので、あまり気にはしていなかった。となりのベッドに「エンガチョ」がいるのは、楽しいことではないし、あたりをはばからぬ手塚の放屁は、低い、大人のような音で、ほとんど凶悪とも感じられたが、寮生活の未来を悲観してはいなかった。
この時点では、まだ長い修学旅行をしていて、たまたま旅館のおなじ部屋に、キタネエ野郎がいるだけだと思っていた。鶴岡雄二「45回転の夏」
湯婆婆 「これっぱかしの金でどう埋め合わせするのさ。千のバカがせっかくのもうけをフイにしちまって!」
【フイ】
むなしい結果。無駄
フイは漢字で書くとと「毀」。「こわす、傷つける、損なう」という意味でフイになるの語源となっています
今日中に二千兩の金を大河内樣へ屆けなきや、去年用立てた千兩の金までがフイになる
野村胡堂「錢形平次捕物控 娘と二千兩」
銭婆 「あたしたち二人で一人前なのに気が合わなくてねぇ。ほら、あの人ハイカラじゃないじゃない? 魔女の双子なんてやっかいの元ね。 おまえを助けてあげたいけど、あたしにはどうすることも出来ないよ。この世界の決まりだからね。 両親のことも、ボーイフレンドの竜のことも、自分でやるしかない。」
【ハイカラ】
しゃれた様子

明治時代に最先端だった立ち襟のシャツを「high collar(ハイカラ―)」といい、次第に「しゃれている、洗練された」という意味合いで広がりました
湯婆婆と銭婆は瓜二つで、服装や身に着けているものもほぼ変わらないように見えるため、ここでは、ハイカラという言葉で、「考え方の違い」を表現しています
「それがさ。冗談にしたんだよ。あの娘がハイカラで生意気だから、からかってやろうって、三人が共同して……」
夏目漱石「吾輩は猫である」